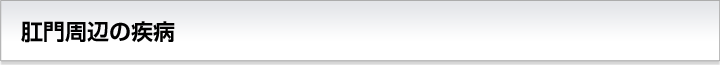
肛門周辺の疾病
痔核(いぼ痔)
→ 詳しくはこちら裂肛(きれ痔)
→ 詳しくはこちら痔瘻と肛門周囲膿瘍
→ 詳しくはこちら嵌頓痔核
→ 詳しくはこちらWHA(ホワイトヘッド肛門)
→ 詳しくはこちら直腸脱
→ 詳しくはこちら直腸腟壁弛緩症(直腸瘤)
→ 詳しくはこちらクローン病の裂肛
→ 詳しくはこちらクローン病の痔瘻
→ 詳しくはこちらFournier's gangrene(フルニエ壊死)
→ 詳しくはこちら膿皮症
→ 詳しくはこちら毛巣洞
→ 詳しくはこちら肛門周囲皮膚炎
→ 詳しくはこちら肛門梅毒
→ 詳しくはこちら肛門尖圭コンジローム
→ 詳しくはこちら白血病
→ 詳しくはこちら痔瘻がん
→ 詳しくはこちら肛門管がん
→ 詳しくはこちらPaget病
→ 詳しくはこちらその他の悪性腫瘍
悪性黒色腫、Bowen病、基底細胞がんなどの皮膚がんがあります。
